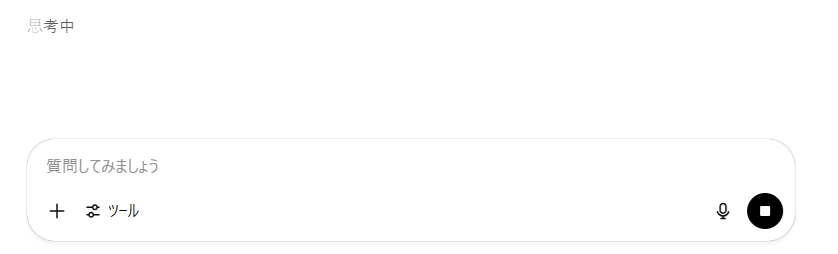
chatgptを使っていていつも思うことが、応答時間をもっと有意義に使うことができないのか、ということ。
特にo4-mini-highでプログラムを書いてもらう場合、思考時間も長く2~3分かかることもあります。
これは、私が20ドルプランだったり、PCのスペックが低いのが問題なのかもしれませんが・・・。
私はいつもこの待ち時間に、youtubeの犬動画やサッカーのハイライトなどを見てしまっています。
また、疲れている時は、ごろごろしてしまってそのまま寝てしまっていることも・・・。
この状態は本当に良くないと思う。
かなり時間を無駄にしてしまっています。
なんというか、この待ち時間が集中力を切らして、別の事をしてしまっている。
待ち時間にリフレッシュすることもできるけど、何となく作業に集中できていなくなってしまうのです。
chatgptや他のAIの待ち時間、レスポンスを有意義に使う方法5選
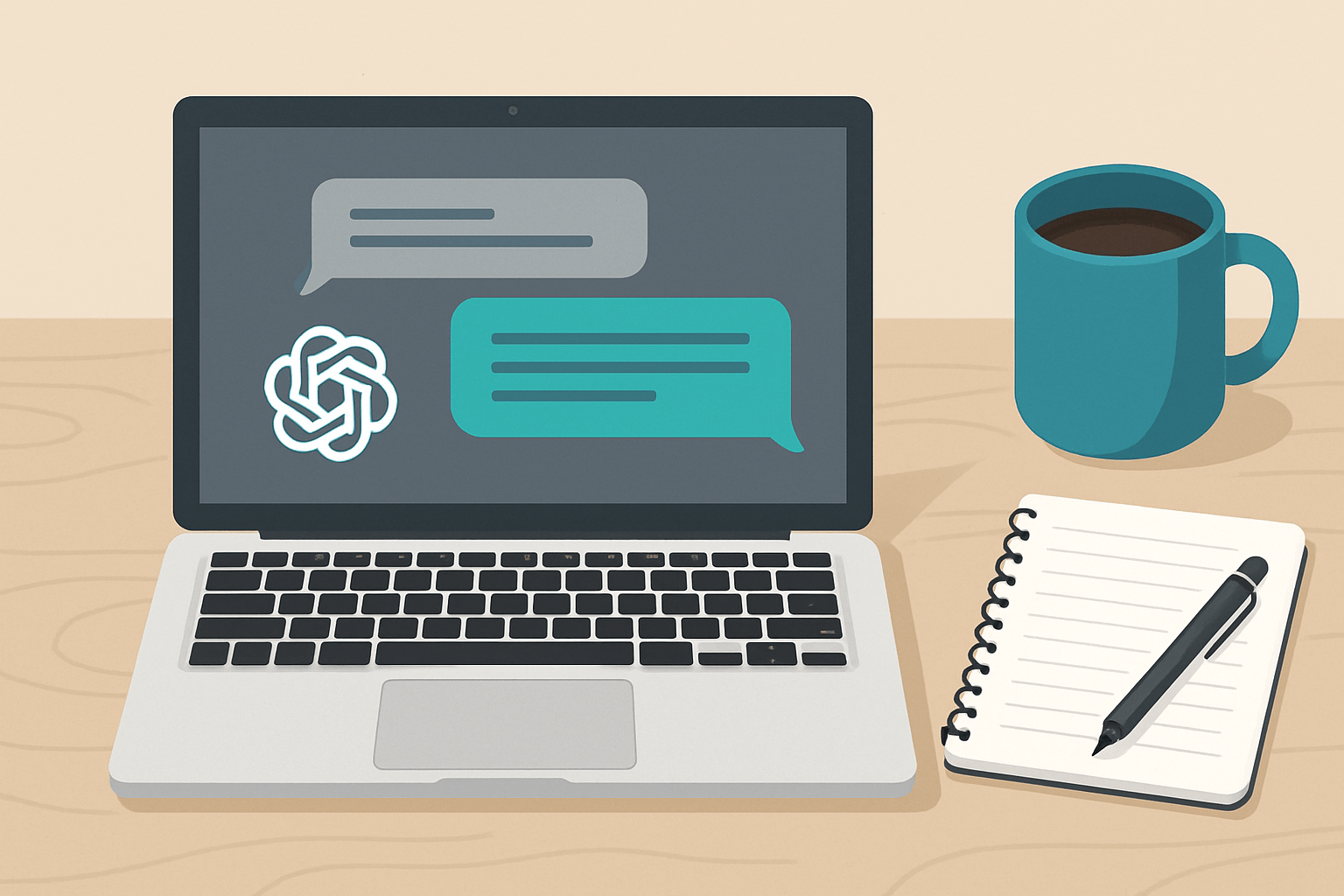
とにかく、AIがチャットや画像などの処理の時間を効率的に使わないと、もったいないです。
その時間を遊んだり、だらけてしまうと、作業時間が余計にかかってしまいます。
でも、数十秒~数分の待ち時間を効率的に使うのはなかなか難しいと思います。
意識がそっちに持っていかれてしまうこともあるので。
そこで、ChatGPTのレスポンス待ち時間を「地味に有意義に」使う方法を考えてみました。
方法1:AI最新情報や関連知識のインプットに使う
AIを使ってのチャットの待ち時間が沢山ある人は、AIを仕事に使っていたり、稼ぐことをしているのではないでしょうか。
私もその一人です。
そこで、AI関連を調べたり、AIの最新情報の動画などを見るのはどうでしょうか。
AIの進化についていくのは大変です。また理解したり学ぶのも。
待ち時間をAI最新情報のインプットを取り入れましょう。
また、別にAIの最新情報でなくても、今自分の行っているAI作業の情報を調べてもいいと思います。
ただ一見、有意義に見えると思うけど、私も実際にやってみましたが、そっちに集中してしまったり、考えたり悩んでしまうこともあります。
そして、今やっているAIとのチャットを放置して、永遠と調べてしまったり。
特に、私のようにASDでIQ67という“思考の切り替え”に苦戦してる人間には、このマルチタスクがなかなかの地獄。
数分間で「ちょこっとだけ情報インプットする」って、実はめちゃくちゃ頭の良い人じゃないとキツい説あります。
おすすめ対策
・視聴する動画や読む記事を“1分〜3分以内”のショート系に絞る
・ブックマークして、AI応答後にじっくり読むようにする
・「とりあえず概要だけ」見るように意識して深掘りしない
2 方法2:目を閉じるだけでも違う?ミニ休憩・軽運動で集中力をリセット
数秒から~数分であれば、目を閉じて瞑想したり、マインドフルネスなどリラックスしてみてもいいと思います。
もしくは、筋トレ。
結構、待ち時間的にもその時間内だけ運動や休憩をするだけなので、余計な思考をしなくても済み、チャットが終わり次第すぐに作業へ移れます。
しかし、そのまま寝てしまうこともあるので、要注意。
もしくは、筋トレにハマってしまい、続けてしまうなど。
1分瞑想orマインドフルネスのやり方
「目を閉じて、呼吸を数えるだけ」。これだけでもちょっと頭がスッキリします。
- 目を閉じて深呼吸3回
- 息を吸う・吐くの長さを意識する
- 「今、自分は待っている」という事実だけに集中する
変にスマホ見たりSNSいじるより、脳が“無”になる時間を挟むことで、作業モードに戻りやすくなります。
立ち上がってちょっとだけ動く
- 肩を回す
- 首を回す
- スクワット3回(ちょっとだけでOK)
- つま先立ち → かかと落とし(地味に気持ちいい)
「え、筋トレ?やだよ…」って思ったそこのあなた。わかる。わかるけど、やってみると地味に効きます。
注意:リラックスの罠
ただし!ここで完全に“くつろぎモード”に入ると危険です。
- ソファでゴロン → 終了フラグ
- ストレッチのつもりがヨガYouTube30分コース
- なぜかそのまま昼寝(私です)
3 待ち時間=補給タイム?食事や軽食でエネルギーチャージ(ただし罠あり)
食事をする時間がない、もったいないときは、このチャット応答待ちの間に、食事をしてみるのもいいと思います。
ただ、私は食事の時は録画しておいた好きなテレビを見るので、落ち着いて食事くらいはしたい。
本当に、AI作業に全てを注いでいる人しか難しいかもしれません。
おすすめ食事(軽食)
チャットが返ってくるまでの間に、
- 一口サイズのおにぎり
- ナッツやチョコなどの軽食
- あらかじめ用意しておいたスープやプロテインバー
こういうもので、軽く脳の燃料補給ができます。特にAI作業って、何気に脳が疲れるからね。
ただし「フル飯」はNG
ここで注意したいのが、ガッツリ食べると集中力が一回リセットされてしまうという点。
「ちょっと食べるだけ」ならアリですが、食べる=休憩モードになる人は要注意です。
おすすめ:咀嚼だけでリフレッシュする
実は「咀嚼(そしゃく)」って、集中力を保つのに地味にいい効果があるそうです。
- ガムを噛む(個人的おすすめ)
- ドライフルーツをつまむ
- スルメ
咀嚼することで脳が適度に刺激されて、眠気やダレ防止になります。これ、完全に作業モードから外れたくない人には結構おすすめです。
4 1分日記 or メモ書きジャーナル
AIがうんうん唸ってる間に、「今やってる作業」「なぜやってるのか」「次の作業でやること」くらいを、箇条書きでもいいからメモしておきましょう。未来の自分が「あれ?どこまでやったっけ?」ってボケるのを防げます。
ポイントは、ガチ日記にしないこと。「今日は風が冷たくて…」とか書き出すと詩人モードに入り、帰ってこれなくなります。
また、AIの作業日記をnoteにアップして毎日継続して行っていれば、ヒットする可能性もある。
AI×稼ぐで日本1のyoutuberあべむつき氏がおすすめしている、「AIの作業日記はやった方が良い」とよく言っていました。
毎日AIとの作業メモをnoteやブログにまとめておくと、意外と「記録メディア」としての価値が出てきます。
「ChatGPTをどう使ってるか」の具体例はまだネットにも少ないので、ニッチな需要に刺さるかもしれません。
5 方法5:インスピレーション収集で“ネタのストック”を作っておく
AIのレスポンス待ち、ぼーっとしてると時間だけが過ぎていきます。
だったらこの時間を**「ネタを拾う時間」**にしてみるのも良いと思います。
使える素材はいっぱいある
- PinterestやInstagramで「デザインの雰囲気」を探す
- X(Twitter)で流れてきた気になるフレーズを保存
- Podcastやボイシーで耳からインスピレーションを得る
- 過去にスクショしたメモや画像を整理する
こういうの、いざ「何か作ろう」と思った時にめちゃくちゃ役立ちます。
「今じゃないけど、そのうち使いたい」ってやつ、ありますよね?
この“種”を拾っておくのが、待ち時間にはちょうどいいと思います。
収集のコツ:保存先をちゃんと決めておく
ただ見るだけじゃダメで、必ずどこかに保存・分類しておくのがコツ。
- メモ帳
- Notion
- Google Keep
- Appleメモ
- Scrapbox
- スクショ+アルバム分け など
後から「あれどこいったっけ?」ってなる未来を防ぎましょう。
散歩感覚でOK
この方法のいいところは、気軽に・だらっとできることです。
無理に集中しなくても、「お、このアイデアいいな」くらいのテンションでOK。
それだけでも、クリエイティブな引き出しがじわじわ増えていきます。
番外編:やってはいけない時間の潰し方(やりがち)
ここまで「待ち時間を有意義に使う方法」を紹介してきましたが、逆に**“やっちゃいけないパターン”**もあります。
全部、私がやったことあります。つまり信用できます。
【NG1】ダラダラSNSを開いてしまう
これはダントツで多いやつ。
- Instagramのリール
- TikTokの無限ループ地獄
- Xの炎上ウォッチ
これらは時間を爆速で溶かします。
「今だけ見る」が通用しない恐ろしい領域。しかもAIの返答が来てても気づかない。
【NG2】スマホゲームの“ちょいプレイ”
「1戦だけ…」と言いながら5戦してる未来が見えます。
特に通知系のゲーム(スタミナ消費とか)を開いた時点で集中力は崩壊します。
AIの返答が戻ってくる頃には「何してたんだっけ?」になってるのは、もはや様式美。
【NG3】布団に入る
論外。
ちょいオマケ:超短時間でできる“地味に効く”待ち時間活用法
- タイピング練習
- LINEやSlack通知の整理
- ペン回し練習(できても意味ないけど、手先は器用になる)
これらは“0.5分”でも実行できる、お手軽ミニゲーム的作業です。
細かいけど、集中力のスイッチを壊さず保つって意味では案外ありかもです。
まとめ:AIの待ち時間、積み重なるとバカにならない
ChatGPTや他のAIのレスポンス待ちって、1回は短くても、積もるとかなりの“時間ロス”になります。かなりもったいないです。
なので、そのスキマ時間を**「自分に合ったちょい使いテク」で潰していく**のが本当に重要です。
- 学びに使うもよし
- 体や心を整えるのもよし
- メモ書きで作業を明確にするもよし
自分のペースで、ムリなく取り入れていきましょう。
「待ち時間=ムダ時間」じゃなく、「準備時間」「整える時間」になるだけで、AI作業の質も自然と上がっていきます。
自分に合ったちょい使いテクニックを1つでも取り入れて、AI作業をもっと快適にしてみてください!
コメント